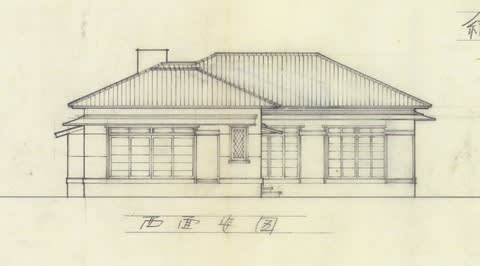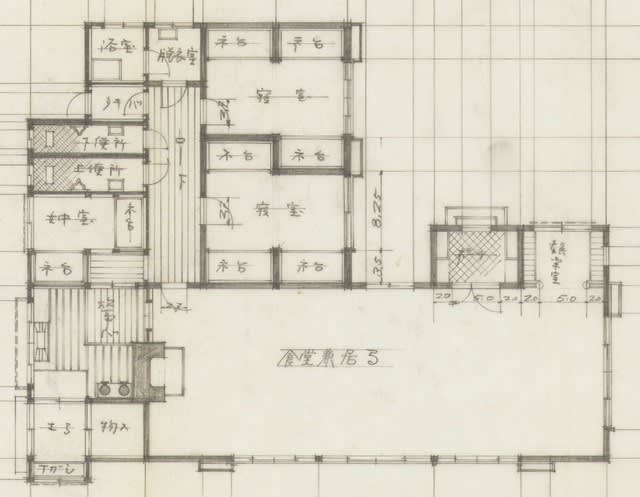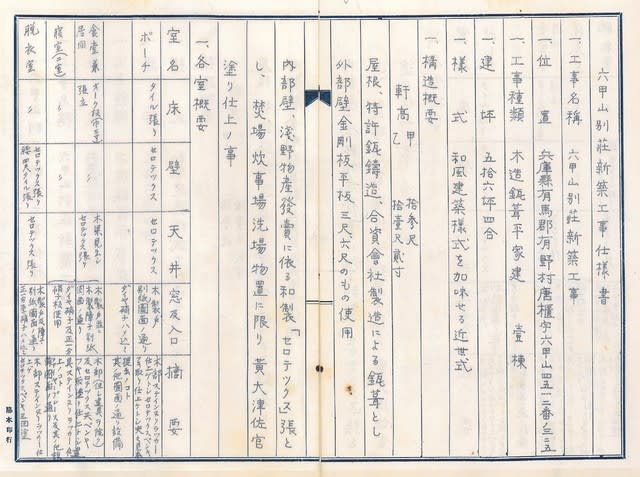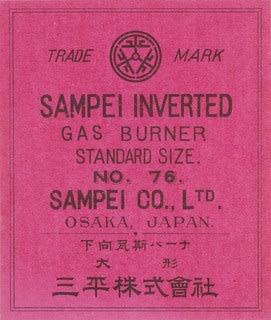前回に引き続き、日本各地の名所を撮影したと思われる写真のご紹介です。
こちらも前回同様、芝川又三郎撮影の写真と思われます。
撮影時期は、又三郎が写真を始めた明治26(1893)年から10年ほどの間ですが、残念ながら撮影地などのメモ書きが殆ど残されておらず、詳細がわからないものもたくさんあります。
ご覧下さった方で、撮影地などがわかる方がいらっしゃいましたら、是非ご教示下さい!
それではさっそく画像をご紹介して参ります。
まずは撮影地がわかっているものから…
![]()
須磨寺(千島土地株式会社所蔵資料P027_001)
「道路の左の柵は若木の桜」と説明が添えられています。
![]()
北野天満宮(同P27_014)
扁額から「天満宮」と読み取ることができます。
![]()
海神社(神戸市垂水区)(同P27_020)
![]()
堂島の大阪商業学校(現・大阪市立大学)(同P27_023)
手前の橋は堂島堀川に架かる「新柳橋」
![]()
熊本第五高等学校(同P27_024)
こちらは又三郎の母校です。
![]()
熊本城(同P27_028)
![]()
耶馬溪 青のトンネル(大分県)(同P27_030)
*
続いて詳細のわからない写真です。
![]()
(同P27_002)
「菅公御手植の松」と記されていますが、菅原道真公が太宰府左遷の際に松を植えた…という伝承は各地に残されていることから、こちらがどの場所なのかは特定できていません。
![]()
(同P27_003)
![]()
(同P27_005)
東大寺南大門のようにも見えるのですが、少し異なるようにも見えます。
![]()
(同P27_018)
こちらは東大寺南大門で間違いなさそうです。
こうして見比べると、上の写真はやはり南大門ではないように思います。
![]()
(同P27_006)
鳥居の扁額の文字が不鮮明ながら「立幡神社」と読めるように思い、検索してみましたが詳細はわからずです。
![]()
(同P27_007)
![]()
(同P27_008)
![]()
(同P27_009)
![]()
(同P27_010)
![]()
(同P27_011)
![]()
(同P27_012)
![]()
(同P27_013)
![]()
(同P27_015)
![]()
(同P27_016)
![]()
(同P27_017)
![]()
(同P27_019)
![]()
(同P27_022)
![]()
(同P27_025)
![]()
(同P27_026)
火災でしょうか?上の写真の被害後の写真のようです。
![]()
(同P27_027)
![]()
(同P27_029)
![]()
(同P27_031)
![]()
(同P27_032)
![]()
(同P27_033)
![]()
(同P27_034)
![]()
(同P27_035)
![]()
(同P27_036)
![]()
(同P27_037)
![]()
(同P27_038)
![]()
(同P27_039)
![]()
(同P27_040)
![]()
(同P27_041)
こちらも前回同様、芝川又三郎撮影の写真と思われます。
撮影時期は、又三郎が写真を始めた明治26(1893)年から10年ほどの間ですが、残念ながら撮影地などのメモ書きが殆ど残されておらず、詳細がわからないものもたくさんあります。
ご覧下さった方で、撮影地などがわかる方がいらっしゃいましたら、是非ご教示下さい!
それではさっそく画像をご紹介して参ります。
まずは撮影地がわかっているものから…

須磨寺(千島土地株式会社所蔵資料P027_001)
「道路の左の柵は若木の桜」と説明が添えられています。
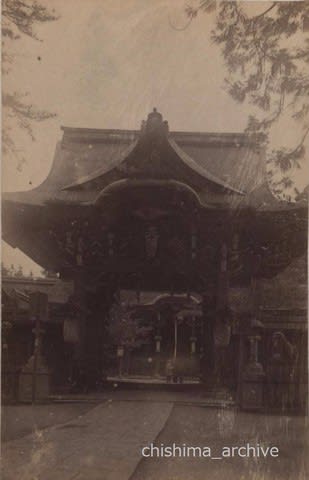
北野天満宮(同P27_014)
扁額から「天満宮」と読み取ることができます。

海神社(神戸市垂水区)(同P27_020)

堂島の大阪商業学校(現・大阪市立大学)(同P27_023)
手前の橋は堂島堀川に架かる「新柳橋」

熊本第五高等学校(同P27_024)
こちらは又三郎の母校です。

熊本城(同P27_028)

耶馬溪 青のトンネル(大分県)(同P27_030)
*
続いて詳細のわからない写真です。
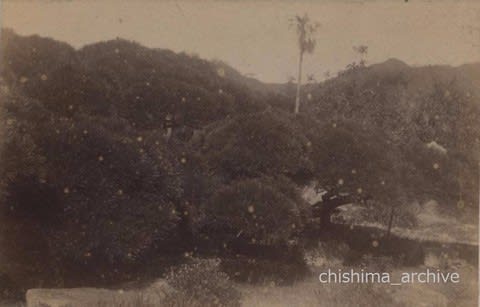
(同P27_002)
「菅公御手植の松」と記されていますが、菅原道真公が太宰府左遷の際に松を植えた…という伝承は各地に残されていることから、こちらがどの場所なのかは特定できていません。

(同P27_003)

(同P27_005)
東大寺南大門のようにも見えるのですが、少し異なるようにも見えます。
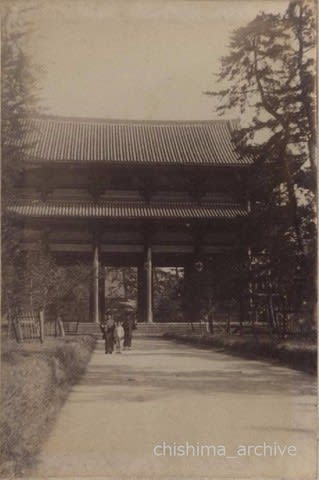
(同P27_018)
こちらは東大寺南大門で間違いなさそうです。
こうして見比べると、上の写真はやはり南大門ではないように思います。
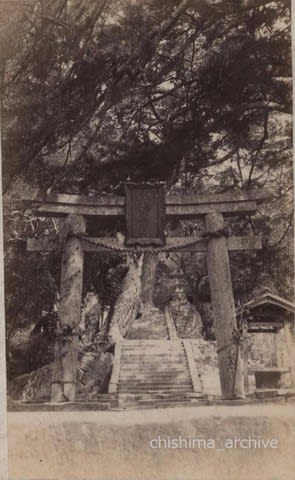
(同P27_006)
鳥居の扁額の文字が不鮮明ながら「立幡神社」と読めるように思い、検索してみましたが詳細はわからずです。

(同P27_007)

(同P27_008)

(同P27_009)

(同P27_010)

(同P27_011)

(同P27_012)

(同P27_013)

(同P27_015)

(同P27_016)

(同P27_017)

(同P27_019)

(同P27_022)

(同P27_025)

(同P27_026)
火災でしょうか?上の写真の被害後の写真のようです。

(同P27_027)

(同P27_029)

(同P27_031)

(同P27_032)
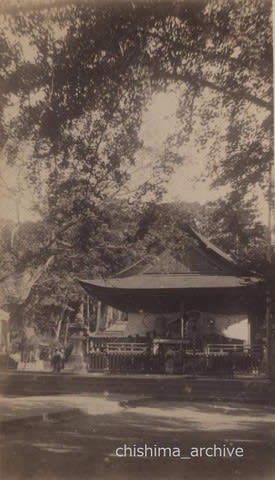
(同P27_033)

(同P27_034)

(同P27_035)

(同P27_036)

(同P27_037)

(同P27_038)

(同P27_039)
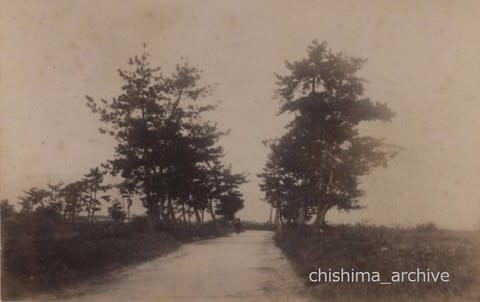
(同P27_040)

(同P27_041)









































 (同P31_049)
(同P31_049)